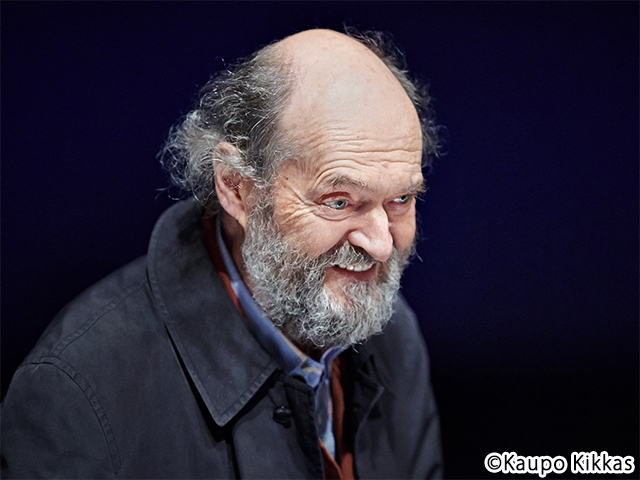7月21~24日、新国立劇場バレエ団は「こどものためのバレエ劇場 シンデレラ(以下「こどもシンデレラ」)」を上演する。夏休みに親子でバレエ芸術にふれられる機会とあって、毎年好評を博しており、内容も濃密。大人が観ても十分に楽しめるクオリティだ。
今年上演される「こどもシンデレラ」では4キャストの主演が組まれている。今回は3年ぶりに主演を務める細田千晶&奥村康祐ペアのリハーサル現場を見学。菅野英男バレエマスターとともに、まずは一つひとつの振り付けをしっかりと確認していた。リハーサルを終えた2人に話を聞いた。(文章中敬称略)
【動画】3分でわかる!こどものためのバレエ劇場「シンデレラ」|新国立劇場バレエ団
■長い付き合いが支える信頼感
――お2人は2015年に「こどもシンデレラ」でペアを組み主演されています。細田さんは今回主演に決まった時はどのようなお気持ちでしたか。
細田 お姉さん役が来るのかなと思っていたので、びっくりしました。菅野さんのアドバイスを受けながら、「この部分は苦手だったなぁ」と思い出しています。
――リハーサルでは王子の登場からパ・ド・ドゥのところを繰り返しやられていました。お2人は『眠れる森の美女』3幕の宝石のヴァリエーションなど、本公演でも何度も組まれています。パ・ド・ドゥに関しては、もうお互いによく知っているという感じで?
細田 そんなことはないです(笑) ソリストとして踊る時に、パ・ド・ドゥは少しありますが、グラン・パ・ド・ドゥはあまりないので、その部分をどうしようかと考えているところです。1人で踊らないよう、もっと空気を読まなくてはと(笑)
――奥村さんは表現力や演技力に定評がありますが、リハーサルは意外とクールでした。
奥村 まだリハーサルが始まってから日が浅いため、女性のサポートをしている時は安心して持てるようになるまで、少し慎重にやっているかもしれません。女性に怪我をさせるわけにはいかないので。ある程度落ち着いてできるまでは感情的になりすぎないようにしています。まずしっかり形の枠組みをつくり、それからだんだん気持ちを入れていきます。
――奥村さんの場合は多くの女性ダンサーと踊っていますが やはり人によってタイミングや支えるポジションなどは全然違うわけですか。
奥村 はい、ダンサーそれぞれ個性があり、ピルエットを回すだけでもみんなそれぞれ違います。
細田さんとはソリストパートで一緒に組むことが何回もあったし普段から見ているし、「こどもシンデレラ」も1度やっているから、詰めて慣れていけば大丈夫だと思います。
本当に何回もリハーサルを繰り返しゲネプロでやっていても、本番の舞台は、幕が開くとどうなるか全然わからないんです。本番に急にテンションが上がる人もいるし、逆の人もいる。客席のお客様の温度や自分の緊張感も加わって、予定していた表現が変わってしまうときもあります。
――舞台の上で瞬時の判断の踊りや表現のやりとりがなされているわけですね。
奥村 サッカーでいえば、パスを受け取るというか。何度も組んでいる相手はすごく楽だし、怖さは感じないですね。細田さんだったら大丈夫だと、僕は信じています(笑)
細田 何をしでかすかわかりませんけど(笑)
![撮影:鹿摩隆司]()
撮影:鹿摩隆司
■プロならではの、互いの芸術性が融合する舞台を
――今王子やシンデレラの表現についてはどのように作っていこうとしているのでしょう。
奥村 お互いプロ同士ですから、それぞれの芸術性や表現をお互いに出し合い、それをすり合わせていく。そうしていった時にどういった形になっているかが大事だと思っています。
――プロ同士の芸術性の融合ですね。細田さんはどのようなシンデレラを思い描いているのですか?
細田 すごくポジティブですよね。逆境にめげない強い心を持っていて、それが成功につながっていくのだと思います。いじめられるかわいそうな弱い女の子ではなく、負けない強さを持ちつつ、信じていたら成功するという、芯の強い女の子かなと。本公演と違いお姉さん役が女性なのでチクチクと、結構いじめられるんですよね(笑)。
![撮影:鹿摩隆司]()
撮影:鹿摩隆司
――本公演のアシュトン振付「シンデレラ」は2人の姉を男性が演じていますが、女性だと妙にリアリティがありますね。王子はどうでしょう。
奥村 シンデレラを苦しい生活から救うヒーローであり、憧れの王子様というイメージです。こどもたちの目はとにかくシビアなので、僕が舞台に出たらすぐに王子様って思ってもらわないと、ずっと王子でいられないんです。普通のお兄さんになっちゃいけない。こどもはその役柄についてそう見えるか見えないかがすごくはっきりしているんです。王子様って思ってもらえるようにがんばらないと。
■こどもの目はシビア。だからこそ表現が"弾ける"
――舞台に向き合うに当たって、本公演と違うところはどういう点でしょう。
奥村 僕らや大人は観る前にこの作品がどういうバレエで……といった知識がある。でもこども達はまっさらな気持ちで観る。そういう子たちに純粋に伝わるように、純粋にお話を楽しんでもらえるようにしようと思っています。
――こどもバレエは何度か拝見していますが、皆さん本公演とは違った弾け方をしている感じがします。
奥村 はい。技術も大事ですけど、「こどもシンデレラ」の場合はまずその役を見てもらわないと、こども達に通じない。通じて初めてきれいだった、シンデレラがお姫様になってよかった、といったところを感じてもらえる。だからこそ、みんな本公演よりも弾けているのかもしれません。
――より演技力が問われるわけですね。こどもは正直でシビアですね。
奥村 感じ方は大人よりも素直で正直だと思います。きれいだと思ったらきれい、よくないと思ったら純粋につまらないと思うし、飽きてしまう。そうした子達をどこまで引きつけられるかがものすごく大変です。子供と遊んだときの感じと同じです。つまらなかったらすぐに飽きますが、面白いと何度も「もう一回!」って要求してきますよね。面白いかつまらないか、どちらかしかない。感動しないと集中できないし。でも一度集中したら、ものすごく集中する。
――上演時間が休憩込みで約1時間25分。20分ほど休憩が入ると各幕約30分ずつくらいですね。
奥村 はい。それならアニメを見るような感じで集中できますよね。だから初めて劇場に来るような子達が本当に感動してくれると一番嬉しいですね。
■ふわっと柔らかな細田&やんちゃな奥村
――お2人のそれぞれの良さを。
奥村 細田さんはふわっとした、独特の空気感があって柔らかくて女性的なところです。
――透明感がありますよね。
奥村 ごくたまに本当に透明になっちゃう(笑)。「疲れた~」って言って壁に寄りかかっていると、彼女は色白なので、本当にすーっと後ろの白い壁と一体化してしまうくらい(笑)。
――文字通り透明……(笑)。
細田 奥村君は役作りも感情もきちっと出すし、「コッペリア」のフランツとか、やんちゃな性格の、少年っぽい役が似合うなぁと。王子役も似合うけど、チャーミングな役は特にいいなと思います。サポートもいろいろな人と踊っているので、いろいろ教えてもらえるし、すごく目線を合わせてくれる。踊りやすい雰囲気や空気を作ってくれるので、演技もやりやすいです。
――ムードメーカー的なところもあるのですね。確かに王子もキャラクターもいけますね。
細田 キャラクターは(「くるみ割り人形」の)ネズミの王様で開花しちゃったかもしれないですよね。一番楽しそうだった(笑)。
――そういえばシーズン・エンディングパーティーで「今シーズンで一番楽しかったのはネズミの王様」と仰ったという話も聞きました。
奥村 「くるみ割り人形」は王子が本当に辛くて大変で、わけがわからないくらいハードだったんです。その反動というのか、ネズミのリハーサルの日がすごく楽しくなってしまい、すごくはっちゃけてしまって(笑)。お面で顔が見えないのに中で表情を作ってノリノリでした。本当はネズミの王様もとてもハードなのですが。
![撮影:鹿摩隆司]()
撮影:鹿摩隆司
■こども達の想像力を越えた感動を
――では最後にお客様にメッセージを。
細田 私自身、小学生くらいの頃に演劇やバレエを観賞する会に入っていたのですが、そうした機会があって、バレエダンサーになりたいという気持ちが強くなりました。だからこども達に少しでも夢や影響を与えられるような舞台にしたいと思います。たくさんのお客様に見にきていただきたいです。
――細田さんは実際にこどもの頃からバレエや演劇を観賞する機会があったわけですね。
細田 バレエを始めたのは4歳からなのですが。でもミュージカルや演劇、バレエを観ることで音楽にもふれ、想像力が養えたと思います。こどもの頃に芸術にふれる機会があったのは今、よかったなと思っています。
奥村 それぞれのこども達の想像力以上のものを与えられればいいなと思います。感動って家の中のできごとやテレビを見るといった日常からではなく、自分の想像力を越えた時に現れるんじゃないかなと思います。だから特に初めて舞台を体験して、想像もしなかった世界にふれたときの感動は貴重な体験じゃないかなと。
――こども達の新しい世界が開けるような、そんな公演を期待しています。そして将来またバレエを観にきていただきたいですね。ありがとうございました。
取材・文=西原朋未