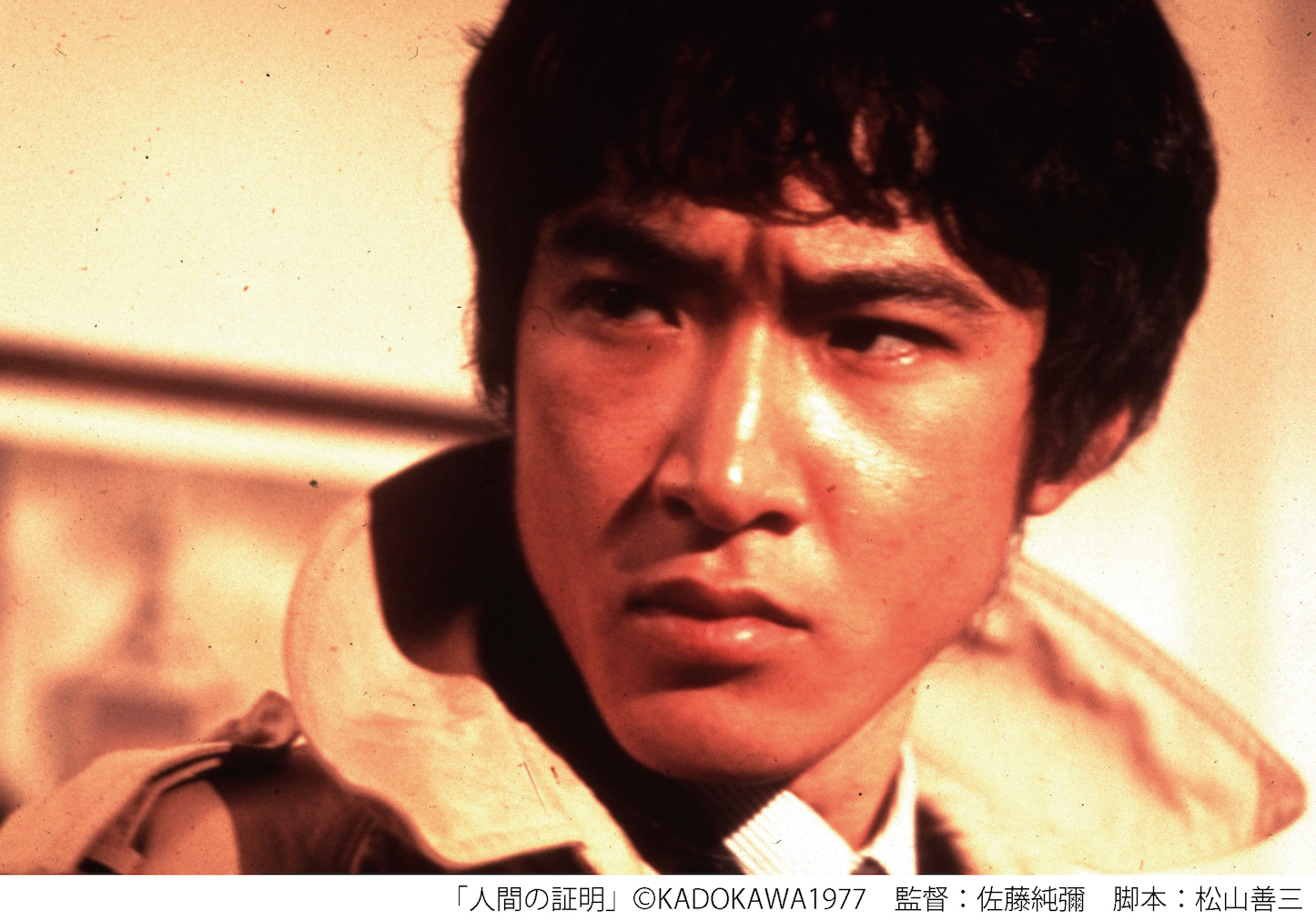2015年に中3で学生音楽コンクールを制した翌年、なんと日本音楽コンクールでも史上最年少の15歳で優勝し、話題を呼んだヴァイオリニスト戸澤采紀(とざわ・さき)。2018年の4月の時点でもまだ高3という若さだが、既に国際的な活躍が期待されているのは言うまでもない。両親ともにプロのヴァイオリニストという家庭に育ったサラブレッドなのだが、実際にインタビューをしてみると、英才教育を受けた才女というだけではない個性的な素顔が垣間見えた。
9月21日(金)に浜離宮朝日ホールで開催される、初の本格的なソロリサイタルの話を軸に、21世紀生まれの新世代ヴァイオリニストはどんなことを考えているのか、様々な角度から話をうかがった。
――ヴァイオリンを本格的に習い出す前に、ピアノを習われていたそうですね。
実は3~4歳で一度、ヴァイオリンをはじめようとしているんです。最初は母にレッスンを受けたら怖かったので、「父に習う!」と言ったんですよ。そしたら、もっと怖くて……30分レッスンを受けて、ヴァイオリンをすぐに辞めました(笑)。それでピアノを習い始めたんです。
――初っ端から衝撃的なエピソードですね……そんなトラウマになりそうな経験があったのに、どうしてもう一度ヴァイオリンを習い始めたんですか?
たまたま父と母が同じオーケストラのなかで弾いているコンサートを6歳のときに聴きに行ったことがあったんですが、その時に「ピアノじゃこの中には入れない」と思って、ヴァイオリンをやりたいと言いました。だから、いまだにオーケストラに入るためにヴァイオリンをやっているという感じなんです。
――その時の曲目って覚えていらっしゃいます?
マーラーの交響曲第7番「夜の歌」でした。(※2007年11月16日(金)、飯守泰次郎指揮の東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の定期演奏会)
――6歳でマーラー!? しかも玄人好みの「夜の歌」とは渋すぎますね!
いま聴いてもよく分からないんですけどね(笑)。それでヴァイオリンを始めることにしたんですが、両親からのレッスンではうまくいかなくて、最初だけは母に手ほどきを受けたんですが、父(東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 コンサートマスター戸澤哲夫)が幼い頃に習っていた保井頌子先生につくことになりました。
――保井先生のレッスンは、どんな感じだったのでしょう?
すごく優しい先生で、怒ることは殆どなかったですね。私がやりたいことを尊重してくれる先生です。小さい頃のヴァイオリンのレッスンって、作り込んで作り込んで、同じことを何回も練習して、それで舞台に出る……というものが多いと思うんですけど、そういうことはあまりせずに音楽的なことを沢山教えてもらいました。
![戸澤采紀]()
戸澤采紀
――中学生ぐらいになると、続々とコンクールで優勝されるようになりますね。いま在学中の藝高(東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校)に入る前は、どんな生活をされていたんですか?
公立の学校に通いながら桐朋学園の音楽教室で通っていたんですけど、父が結構厳しくて(笑)、中学生の頃が一番勉強を頑張っていました。テスト前などは一週間、ヴァイオリンよりも勉強している時間の方が長かったですし、茶道部にも入っていたので部活との両立も頑張っていました。
――高校生の現在は、普段どのくらい練習されるんでしょうか?
平日は学校があるので3時間ぐらい。学校がない日は大体7時間~10時間とか。食べているときと、寝ているとき以外は1日中弾いているときもあります。他にすることもないですから(笑)。
![ヴァイオリンケースの中には……]()
ヴァイオリンケースの中には……
――それだけ熱心に練習されてきたこともあり、これまで様々なコンクールで優秀な成績を収めてきたわけですが、その中で特に思い出深いものはありますか?
学生音楽コンクールかなぁ。小6から毎年、学生音コンを受けてきて、4回目の中3でやっと全国大会で1位を獲れたんです。学生音コンには3つラウンドがあるんですけど、日コン(日本音楽コンクール)と違って、課題となるのは各ラウンドで1曲ずつなので、1曲にかけられる時間がもの凄く長いんです。だから学生音コンには、1曲の精度をどれだけ上げて、音楽的に内容をつめていくという、そういう細かい勉強を教えてもらいましたね。それまで保井先生には好きにやらせてもらっていたので、自由な感じだったんですけれども、学生音コンのお陰でプロになるにあたっての細かい練習の仕方などが身についた気がします。
――学生音楽コンクールに優勝された際も、その翌年の日本音楽コンクールでも、シベリウスのヴァイオリン協奏曲を本選で演奏されていますね。
この曲の何が好きかって聞かれると、自分でも正直よく分からないんですけど、やっぱりヴァイオリン協奏曲のなかでは一番好きです。音楽祭に参加するため、(シベリウスの出身地である)フィンランドに何回か行ったんですが一番最初に行ったときにシベリウスの協奏曲を弾いて、スカラシップ(奨学金)を貰ったんです。そういう意味でもこの曲には凄く思い入れがありますね。
――いつ頃から好きになったか覚えていらっしゃいますか?
記憶にないですね(笑)。最初に演奏したのは、中学2年生かな。2014年にかながわ音楽コンクールで大賞を獲ったときにオーケストラと共演する機会をいただいて、そこでシベリウスを選んだんです。
![戸澤采紀]()
戸澤采紀
――他にはどんな音楽がお好きですか?
マーラー・オタクなので私は(笑)。マーラーに関しては交響曲の2番(「復活」)、9番、10番を愛してやまないんです。特に9番は、特別な時にしか聴いちゃいけないっていう風にしていて。だから日コンの前日も、ティボール・ヴァルガのコンクールの本選の前日も、受験の前日も、全部マーラーの9番を聴いていました。両親を部屋から追い出し、部屋を真っ暗にして、スピーカーをすっごい大音量でかけて、それで大号泣してすっきりして本番に臨むんです。
――マーラーでヴァイオリンをはじめ、今もマーラーを心の支えにして音楽を続けていらっしゃることがよく分かりました(笑)。さて、9月21日(金)に東京でリサイタルを開催されるそうですね。
リサイタル自体は何回かやらせていただいたこともあるんですけれど、ここまで大きいホールでやったことはないので私も凄く楽しみなんです。
――会場は、国内屈指の音響を誇る浜離宮朝日ホールですが、どのような印象をもたれていますか?
(父が出演する)モルゴーア・クァルテットの演奏を聴きに何回か行ったことがあります。ダイレクトではありつつも、いい感じのふわっとした響きで後ろから包み込んで音を届けてくれるイメージがありますね。弦楽器特有のちょっとしたニュアンスなども、よく聴こえてくるようなホールだというのは聴きながら思っていたので、演奏するのが今から楽しみです。
――そして東京公演に先立って、8月10日(金)には岡山公演として早島町町民総合会館 「ゆるびの舎」文化ホールでも演奏が予定されています。
実は母の実家が岡山なんです。既に去年、母の姉が主催してくれて演奏をしているんですが、今年も演奏できるのは嬉しいです。
![取材中、ちょっとした演奏も]()
取材中、ちょっとした演奏も
――リサイタルは、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタのなかでも人気の高い第18番(ト長調,K 301)から始まりますね。
明るい雰囲気でコンサートのオープニングを飾れたらなと思って選びました。これは私にとって懐かしい曲で、いつだったっけ……中学2年生でサロンでコンサートしたときにオープニングで弾いたのかな? 自分の若々しさを……まだかろうじて若いので。
――10代ですから、充分すぎるほど若いですよ(笑)。続いては20世紀を代表する大ヴァイオリニストのミルシテインが作曲した無伴奏による「パガニーニアーナ」。これは有名なカプリース第24番をテーマとした変奏曲ですね。こちらを演奏するのは……
演奏するのは初めてです。2014年の『ヴァイオリン フェスタ トウキョウ』で山根一仁さんの演奏を聴いて「スゴいな!」と思ったのがきっかけなんです。音楽家というよりは、ヴァイオリニストとしての技術というか自分の魅力を魅せるという意味で、もの凄く良い曲。技巧的ではあるんですけど、全体を通して凄くセンチメンタルな感じもあったり、派手なところもあったり。変化に富んでいるので、モーツァルトの後に雰囲気を一変させてガラッと変えるっていう意味で選んでいます。
――続けて、もう1曲無伴奏が続きます。イザイの6つの無伴奏ヴァイオリン・ソナタより第5番。正直、6曲のなかでは演奏される機会の多くない作品ですよね。
イザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタに関しては去年6番をコンクールで演奏したんですけど、その前から5番が大好きで大好きでしょうがなくて。何故かというと、私はレオニダス・カヴァコスっていうヴァイオリニストが大好きなんですけど、この曲は彼の十八番なんです。
――それだけ戸澤さんを魅了する第5番の聴きどころは、どのあたりでしょうか?
イザイっていうと超絶技巧をみせるというか、音楽の内容も派手で民族的で素晴らしいんですけど、結構技巧的でテクニシャンな感じなところがありつつも、この5番はすごく情景が浮かんでくるというか、ものすごい色彩豊かなんですね。そういうところがもの凄い好きです。なぜか2楽章構成だったりして、まとめ方が結構難しかったりするので、なかなか日本では皆さんやられませんけど。
![戸澤采紀]()
戸澤采紀
――休憩を挟んで、今度はベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第8番から後半がはじまります。
この曲は去年の日本音コンの課題だったんです。コンクールを聴きに行ったんですが、自分だったらどういう風に弾けるかをやってみたいなと思ったんです。ベートーヴェンのソナタってそれぞれ個性が豊かで、色々な違いがみられるんですけど、8番に関してはそれが全部凝縮されているようなイメージがあります。ベートーヴェンの明るい面と、歌うような面がつまった作品です。
――プログラムのラストを飾るのはプーランクのヴァイオリン・ソナタです。
この曲は、2年前に日本音コンを獲ったときの三次予選の課題でした。コンクールで弾くまでは知らなかったんですが、それぞれの楽章に特徴的な個性があって、初めて聴いた時にそれはそれは凄い曲だなと思って。よくよく調べたら、書かれた動機もなかなかに凄くて(※独裁政権に反抗して銃殺された詩人ガルシア・ロルカの思い出に捧げられている)。2年前のコンクールの時に聴いてくださった方もいると思うので、過去の自分よりももっと表現して成長した面もお見せ出来たらなと。
――共演するのは丸山晟民(まるやま・あきひと)さん。なんと彼もまだ今年で20歳という若いピアニストです。
共通の友人がいたり、母のヴァイオリン教室の伴奏をしてもらったりで知り合って、共演する前から友達みたいな感じでした(笑)。ピアニッシモで弾くときって、普通は密度まで落ちちゃったりして良い音を出すのは難しいと思うんですけど、ピアニッシモでも物凄い綺麗な音で、キラッと光るような魅力のある音を出すピアニストです。特にベートーヴェンなどは、一緒にやったら洗練された音楽になるんじゃないかなと思ってお声がけさせていただきました。
――もっとベテランの伴奏ピアニストと共演するという手もあったかと思うのですが、なぜ今回、同世代のピアニストとの共演を選んだのでしょう?
私が通っている藝高では、試験の伴奏もみんな学生なんです。年が近い方がお互いに言いやすいし、言ってもらいやすい。コンチェルトとかでもアンサンブルとして出来るっていうのが魅力だと感じました。だから今回も丸山さんに声かけたんです。ヴィルトゥオーゾ・ピース(超絶技巧の小品)をいっぱいというよりは、ソナタをいっぱいやりたいなと思っていたのもあります。そもそもデュオとしてやりたかったんです。
――そう考えるようになったのは、いつ頃からですか?
自分がソロとして弾くのは、実はずっとあんまり好きじゃなくて。責任重大というか……いや、どちらにしろ責任重大なんですけど。やっぱり誰かと一緒に弾くというのがもの凄く好きなんですよね。環境的にも、「オーケストラが大好き!」みたいな人が集まった家なので(笑)。そういう風に育っちゃいました。
![戸澤采紀]()
戸澤采紀
――じゃあ、オーケストラだけでなく、室内楽もお好きなんですか?
いま、ふたつカルテットを組んでいて、今年はそれで活動していたりとか、あとは学校のアカンサスコンサートに参加したり。フィンランドの音楽祭も最初はソロで参加したんですけれど、そこでスカラシップを頂いて、次からはヤングアーティストとして呼んでいただいたので、ヨーロッパの若手の人たちとも一緒に室内楽をやったりしています。
――今後はどんなヴァイオリニストを目指されていかれますか?
ここ数年、コンクールとかで色んな人に声をかけていただいてお話しさせていただく中で、「将来はオーケストラに入りたい」と言うと、どうしても「なんで!? もったいない!」っていう風に言われてしまって。
日本では、オーケストラ・プレイヤーよりもソリストのほうが秀でているというような見方があるのかもしれないですが、絶対そんなことはなくて。それぞれに魅力があって、本当に一流の演奏家というのはソロも室内楽もオーケストラのなかでも、コンサートマスターじゃなかったとしても、弾けなきゃいけないというのが私のなかでずっと思っていることなんです。だからこれから活動していくにあたっては、そういう意味での“一流の演奏家”を目指しつつ、努力していきたいなと思っています。
――最後に記事をお読みになっている皆さまへ、リサイタルに向けたメッセージをお願いします。
コントラストが効いたメリハリのあるプログラムになっていて、なおかつ日本ではあまり演奏される機会が少ないけれど、実はとても素晴らしい曲というものをいっぱい揃えました。メジャーじゃない曲で、その魅力を精一杯伝えるっていうのは、難しいことだとは思うんですが、そういう曲でもお客様に満足していただきたい。自分なりにそういうところも頑張ってしっかり勉強して、演奏したいなと思うので、楽しんでいただけるように頑張ります。是非いらしてください!
![取材から解放された瞬間を激写]()
取材から解放された瞬間を激写
インタビュー・文=小室敬之 撮影=山越 隼